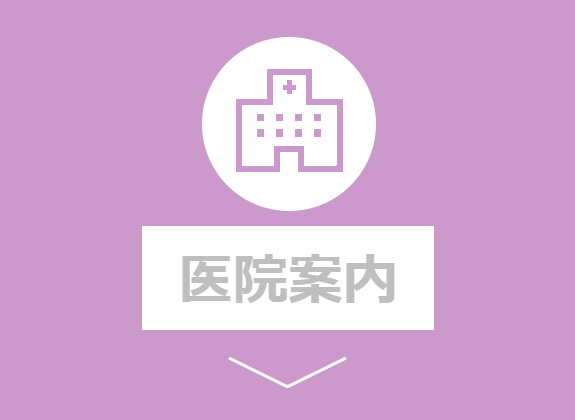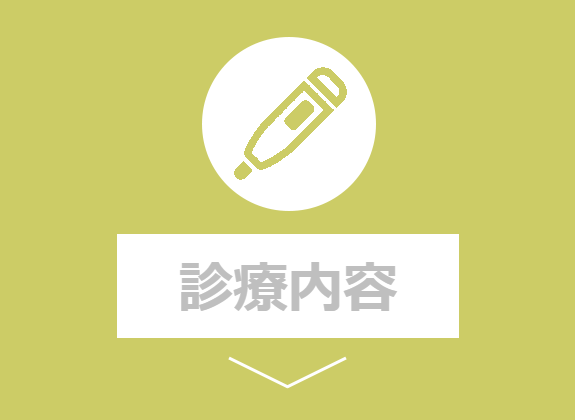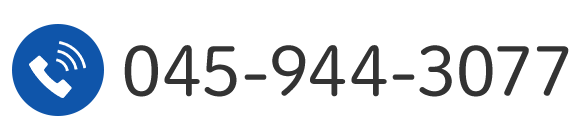
当院は4月より新医院に移行しました。
「センター南消化器内科・内視鏡クリニック」
4月1日の院長交代に伴い現院長は非常勤となり、新院長として
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 中村大樹 医師が着任しました。
新クリニック名は以下のとおりです。
「センター南消化器内科・内視鏡クリニック」
https://centerminami-naishikyo.com
当院は、消化器内科・内視鏡科として出発し、皆様のお役にたつ施設を目指します。


山崎晴市 医師 4月以降の診療について
水曜日
4月:午前9時~12時・午後13時30分~16時5月:午後12時30分~16時
- ご予約をお取りしますので、受付窓口までお問い合わせください。
- 直接ご来院いただくことも可能です。
- 「センター南消化器内科・内視鏡クリニック」のホームページからWEB予約が取れます。
「センター南消化器内科・内視鏡クリニック」について
地域のかかりつけ医と専門性を両立するクリニック
消化器専門医による診断と苦痛の少ない内視鏡検査を提供します。